山形花笠まつりで使う「花笠(はながさ)」は、これまで100%山形県内(やまがたけんない)で作られていたそうです。
ですが2024年、作り手の高齢化・減少により「花笠が用意できない」という事態に。
そこで、まつり存続のために、今回初めて海外・ベトナムで花笠生産に踏み出したそうです。
今回は、この花笠まつりの歴史と花笠について、特に高齢化・減少による作りて不足について記事を書いてみたいと思います。
他の地域のおまつりでも同じような事が起こる可能性もあるので、少しでも今後の事を考えるきっかけになれば幸いです。
それでは今回もよろしくお願い致します。
まつりで使われる花笠の9割以上を作っている尚美堂さん
今回、初めて尚美堂(しょうびどう)さんの事を知りました。
花笠まつりで使われている花笠の9割以上を作っているそうです。
同じ山形県内にいながら、これまで知りませんでした。
尚美堂さんは山形県にある老舗のセレクトショップで、花笠まつりで使われる花笠の制作で有名です。山形県山形市(やまがたけん やまがたし)に店舗があり、伝統的な工芸品や民芸品も取り扱っています。
店舗のご案内
七日町旭銀座店 山形県山形市七日町2-7-18 ナナビーンズ1階
エスパル山形店 山形県山形市香澄町1-1-1 エスパル山形2階
花笠まつりの歴史について
山形県の花笠まつりは、毎年8月5日から7日にかけて開催される伝統的なお祭りです。
その起源は江戸時代にまで遡り、当時は「花笠踊り」として知られて知られていました。
・起源:17世紀から18世紀の江戸時代、山形で始まったとされています。初めは、農民たちが豊作を祈願するために行われていた踊りでした。
・近代化:明治時代に入ると、現代のような形式に近づき、地域のお祭りとして発展しました。
・戦後の復活:第二次世界大戦後、1946年に「花笠音頭」が作られ、これが一躍有名になりました。これにより、お祭りは全国的に知られるようになりました。
・公式化と拡大:1963年に初めて「花笠まつり」として公式に開催され、以降、規模が拡大し、観光イベントとしても重要な位置を占めるようになりました。
・現在の形:今では、約100万人以上の観客を集め、参加者も数千人規模で、花笠をかぶり、華やかな衣装で踊る様子が特徴的です。
この「花笠まつり」は、山形の夏の風物詩として、また地域の文化と伝統を後世に伝える重要なイベントとなっています。
作り手の減少
かつて花笠の生産に携わっていた作り手がピーク時の約30人から6人にまで減少しました。これは主に高齢化による影響で、後継者が育たなかったことが原因です。
花笠まつりの存続
花笠まつりを存続させるためには、花笠の供給が不可欠です。作り手不足による国内で必要な量を確保できなくなったため、海外での生産を検討する必要が生じました。
ベトナムで生産開始
2025年の花笠まつりに向けて、ベトナムで1500個の花笠を生産する計画が進められ、早ければ3月末に届く予定です。
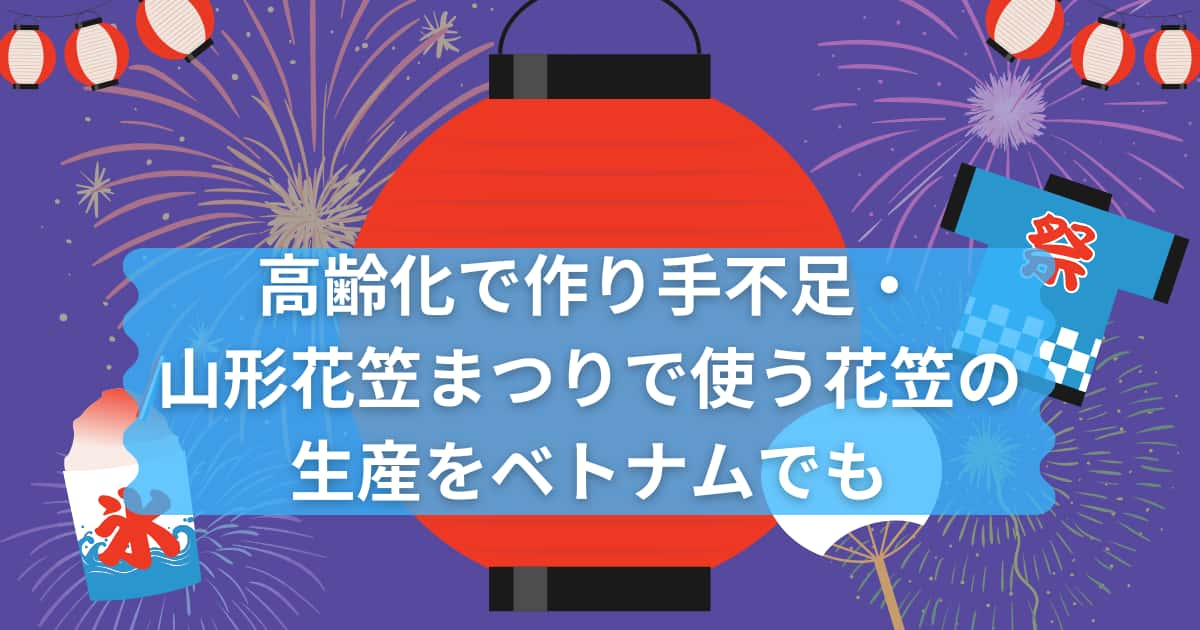
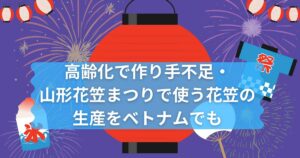
コメント